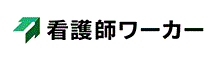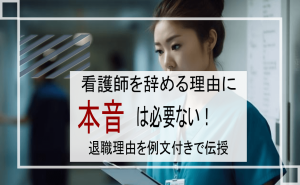「助産師になりたい!」
「どうすればなれるの?」
と考えていませんか?
助産師になるには、「看護師資格」と「助産師資格」の両方を取得する必要があります。
なお、受験資格を得るには看護師・助産師養成課程を卒業しなければならないため、資格を一切保有していない方の場合、助産師になるまでに最短でも4年かかります。
本記事ではこれまで転職のプロとして医療分野の転職支援をしてきた私が、助産師になるための方法や助産師の仕事内容について解説します。
- 【学歴・経歴別】助産師になるための最短ルートと全ステップ
- 助産師になるための学校の選び方
- 助産師国家試験の難易度・合格率と勉強法
- 助産師になるために必要な資格
- 【必見】助産師になるまでに費用は80~150万円かかる!
- 助産師に向いている人の4つの特徴
- 【要注意】助産師に特有の仕事の苦労
- そもそも助産師の仕事とは?
- 【FAQ】助産師を目指す方によくある質問
全て読めば、助産師になるために自分がやるべきことや、必要な期間、費用がわかるでしょう。
| 看護師転職サイト | サービスの特徴 |
|---|---|
詳細を見る | 公開求人数:22万件以上|満足度:4.3 ・アンケート満足度の人気◎ ・業界トップクラスの求人数 20代30代40代 全国 |
| 公開求人数:約20万件※|満足度:4.2 ・有名メディア『ナース専科』の運営企業が提供 ・応募先施設への猛プッシュが力強い 20代~40代 全国 | |
公式サイト 詳細を見る | 公開求人数:約23万件|満足度:4.0 ・地方の求人にも強い ・施設の内部事情にも精通したサポート 20代30代40代 全国 |
| 公開求人数:約6.5万件|満足度:3.9 ・スピーディーかつ質の高い提案 ・地域ごとに専門のキャリアパートナーが対応 20代30代40代 常勤パート・非常勤 全国 | |
5位:マイナビ看護師 公式サイト 詳細を見る | 公開求人数:約8.5万件|満足度:3.6 ・求人検索システムの使いやすさが◎ ・一般企業・治験関連企業にも強い 20代30代40代一般企業 常勤パート・非常勤全国 |
※2025年11月17日更新
※弊社が実施した独自アンケートの結果に基づきます
※本記事は看護roo!、レバウェル看護、マイナビ看護師、看護師ワーカー、ナース専科 転職などのPRを含みます。
【学歴・経歴別】助産師になるための最短ルートと全ステップ
助産師を目指す道のりは、あなたの現在の状況によって大きく異なります。高校生、既に看護師資格を持つ方、社会人や主婦の方それぞれに最適化されたルートをご紹介します。まず共通して理解しておくべきは、助産師になるには看護師資格と助産師資格の両方が必要だということです。
助産師資格取得の基本原則
助産師法第3条により、助産師になるためには「保健師助産師看護師法に基づく看護師の免許を受けている者」であることが必須条件となっています。つまり、どのようなルートを選択しても、まず看護師資格を取得し、その後に助産師資格を取得するという二段階のプロセスが必要です。
この基本構造を理解した上で、あなたの現在の状況に最も適したルートを選択していきましょう。
高校生から助産師を目指すルート(4-5年間)
高校卒業後に助産師を目指す場合、効率的なルート選択が将来のキャリア形成に大きく影響します。
最短ルート:4年制看護大学での統合コース
最も効率的なのは、4年制看護大学で看護師課程と助産師課程の両方をまとめて修了する方法です。このルートが、ゼロから助産師を目指す過程では最短となります。
4年次に助産師課程を履修することで、看護師と助産師の両方の国家試験受験資格を同時に取得できます。卒業と同時に両方の資格を得られれば、22歳という若さで助産師としてのキャリアをスタートできます。
ただし、助産師課程への進学には学内での選抜試験が実施されることが一般的です。成績、面接、小論文などを総合的に評価されるため、入学時から助産師を目指す明確な意志と継続的な努力が必要になります。
標準ルート:看護師資格取得後の助産師養成校進学
選抜試験に不安がある場合や、より確実に助産師を目指したい場合は、まず看護師資格を取得してから助産師養成校に進学する方法もあります。
看護師養成課程は以下の選択肢があります:
- 4年制看護大学:看護学士号を取得でき、将来の選択肢が広がる
- 3年制看護専門学校:実践的な教育で早期に資格取得、学費も比較的安い
- 3年制短期大学看護学科:大学と専門学校の中間的な位置づけ
看護師資格取得後、1年制の助産師養成校に進学します。助産師養成校には以下の種類があります:
助産師養成施設の種類:
- 助産専門学校:1年間の集中的なカリキュラム
- 大学院(助産課程・助産専門職大学院):2年間でより高度な教育
- 大学(助産学専攻科):1年間、大学レベルの充実した教育
- 短期大学(助産学専攻科):1年間の実践的な教育
このルートのメリット:
- 若いうちから専門性を身につけられる
- 長期的なキャリア形成が可能
- 同世代と比較して専門職としての優位性がある
このルートの注意点:
- 長期間の学習継続が必要で、途中での進路変更が困難
- 経済的負担が大きく、家族の理解と支援が不可欠
- 強い意志と明確な目標設定が必要
看護師から助産師を目指すルート(1年間)
既に看護師資格を持っている方にとって、助産師への道のりは最もシンプルで効率的です。
最短1年での資格取得が可能
看護師資格保有者は、助産師養成校で1年間の課程を修了することで助産師国家試験の受験資格を得られます。タイトな履修スケジュールの養成校では1年間、比較的柔軟なカリキュラムの場合は2年間程度の期間が必要です。
助産師養成校での学習内容
1年間という短期間ですが、非常に密度の濃い学習が求められます。
前期(4月-9月)の主な学習内容:
- 助産学概論・助産診断技術学
- 母性看護学・新生児学・産科学
- 助産管理学・法律と助産師
- 母乳育児支援・家族計画
後期(10月-3月)の実習中心カリキュラム:
- 分娩介助実習(正常分娩10例以上の介助体験)
- 継続事例実習(妊娠期から産褥期まで一貫したケア)
- ハイリスク妊産婦ケア実習
- 地域母子保健実習
看護師経験が活かされる場面
看護師としての臨床経験は助産師養成課程で大きなアドバンテージとなります。特に以下の経験は高く評価されます:
- 産婦人科・NICU勤務経験:専門知識と実践経験が直接活用できる
- 救急・ICU勤務経験:緊急時の判断力と冷静な対応能力
- 外来勤務経験:患者・家族とのコミュニケーション能力
このルートのメリット:
- 最短期間での資格取得
- 看護師としての経験と知識を活用できる
- 卒業後、即戦力として高い評価を得られる
このルートの注意点:
- 助産師養成校への入学競争が激しい(倍率2-5倍程度)
- 1年間の集中学習で体力的・精神的負担が大きい
- 学習期間中は収入が減少または途絶える
社会人・主婦から助産師を目指すルート(4-5年間)
医療業界未経験の社会人や主婦の方でも、適切な計画と強い意志があれば助産師を目指すことは十分可能です。
段階的なキャリアチェンジ戦略
社会人からの転身では、いきなり看護師養成課程に進学するのではなく、段階的にアプローチすることをお勧めします。
第1段階:医療現場での経験積み まったく未経験から医療業界に興味を持った方は、看護助手や介護助手として医療の現場で勤務してみることも有効です。これらの職種は就業先によって未経験者でも勤務可能で、医療従事者をサポートしながら現場を学べます。
第2段階:看護師資格の取得 医療現場での経験を積んだ後、または並行して看護師資格の取得を目指します。社会人には以下の選択肢があります:
社会人向けの看護師養成課程:
- 4年制看護大学(社会人特別選抜):夜間部や土日開講コースもあり
- 3年制看護専門学校:実践的で効率的、社会人支援制度も充実
- 准看護師ルート:まず2年で准看護師、その後2年で看護師資格
第3段階:助産師養成課程への進学 看護師資格取得後、助産師養成校で1年間学習します。
家庭・仕事との両立戦略
社会人・主婦が学習を継続するためには、綿密な計画と家族の協力が不可欠です。
時間管理のポイント:
- 早朝・夜間・休日の活用:家族が寝静まった時間の有効活用
- スキマ時間の最大化:通勤時間、昼休み、待ち時間での学習
- 学習環境の整備:集中できる専用スペースの確保
家族との協力体制:
- 家事・育児の分担:パートナーや家族との役割分担の明確化
- 外部サービスの活用:家事代行、学童保育、一時保育の利用
- 理解と応援の獲得:家族に夢と計画を共有し、応援してもらう環境作り
経済面での準備戦略
長期間の学習には相当な費用がかかるため、計画的な資金準備が必要です。
活用できる支援制度:
- 専門実践教育訓練給付金:最大224万円の支給(条件あり)
- 自治体の奨学金制度:地域によって独自の支援制度
- 医療機関の奨学金制度:卒業後の勤務を条件とした資金支援
働きながら学ぶ場合の学校選択
主婦・社会人の方には、柔軟な通学スケジュールの養成校がお勧めです。週3日程度の通学で学べる学校であれば、家庭や仕事と両立しながら助産師を目指しやすくなります。
ただし、実習期間は毎日通学が必要となります。履修時間が規定に満たない場合は実習期間が延長されるケースもあるため、事前の準備と調整が重要です。
働きながら勉強する成功のポイント
「なぜ助産師を目指すのか」「助産師資格を取得してどうなりたいか」といった目標と将来像を明確に定めておくことが成功の鍵です。仕事と両立しながら専門的な知識を身につけることはハードルが高く、モチベーション維持が最大の課題となるからです。
また、看護師として働きながら助産師を目指す場合、勤務先の病院によっては奨学金制度やバックアップ体制が整っている場合があります。人事部や看護部に相談して、利用できる制度がないか確認してみましょう。
このルートのメリット:
- 豊富な人生経験を活かした深いケアができる
- 患者・家族との信頼関係を築きやすい
- 多様な働き方の選択肢がある
このルートの注意点:
- 長期間の学習継続が必要で強い意志が求められる
- 家庭・仕事との両立が困難な場面がある
- 年齢による体力面での制約がある場合もある
各ルートの成功事例
高校生ルート成功例:看護大学統合コース卒業のAさん(26歳) 「高校時代から助産師への憧れがあり、看護大学の統合コースを選択しました。4年次の選抜試験は緊張しましたが、1年次からコツコツと成績を維持していたおかげで合格できました。現在は年間500件以上の分娩を扱う総合病院で働いており、同世代の看護師より専門性が高く評価されています」
看護師ルート成功例:NICU経験5年のBさん(32歳) 「新生児ケアの経験を活かして助産師になりたいと思い、養成校に挑戦しました。1年間は本当に大変でしたが、NICU での経験が実習で大いに役立ちました。卒業後はハイリスク分娩を多く扱う周産期センターで働いており、やりがいを感じています」
社会人ルート成功例:元会社員のCさん(44歳) 「30代後半で医療業界に転身を決意しました。まず看護助手として2年間現場を経験し、その後看護学校に進学。家族の協力があったからこそ続けられました。助産師になった今、人生経験の豊富さが患者さんとの関係構築に活かされていると実感しています」
あなたの現在の状況と将来の目標を照らし合わせて、最適なルートを選択してください。どのルートを選んでも、助産師という素晴らしい職業への道のりに変わりはありません。
助産師になるための学校の選び方
助産師の学校を選ぶ際は、どの方法で合格を狙いたいかを基準にしましょう。
それぞれ、解説していきます。
同時に2つの国家試験合格を狙うなら「助産師養成課程のある4年制大学」
同時に合格を狙いたい方は、「助産師養成課程のある4年制大学」を選ぶと良いでしょう。
なぜなら、卒業前に看護師と助産師の国家試験を受けて、両方合格した場合、卒業後すぐに助産師として働けるからです。
ポイント:4年生の看護大学を選ぶ際に確認すること
- 助産師養成課程があるか確認。(すべての看護学科に助産師養成課程が用意されているわけではない)
- 大学の入試倍率と、養成課程の定員を確認。(助産師養成課程の定員は大学によって異なる)
- カリキュラムの定員や優先枠について調べる。(選択式の「カリキュラム」受講で受験資格を得られる場合もある)
ただ、同時に受験するのは効率的ですが、学生生活は多忙となるでしょう。
そのため「何より、早く試験に合格したい」「忙しくてもやり抜ける」という強い意志がある方におすすめします。
看護師→助産師の順に狙うなら「助産師養成所」
看護から助産師の順に狙うなら、「3年制の短大か看護専門学校」を卒業して看護師国家試験を受けた後、「助産師養成所」に入学して助産師国家試験を目指しましょう。
補足:3年制短大・専門学校と助産師養成所について
| 3年制短大 | 3年制専門学校 |
|
|
| 助産師養成所 (1年) | |
| |
ただ、複数の学校に通う必要があるため、学費の負担が増えます。
ゆえに、「じっくりと長期にわたり勉強したい」「金銭的負担が大きくても構わない」という方には、上記の方法がおすすめです。
助産師養成課程 学校種別比較表
| 学校種別 | 学費目安 | 学習期間 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4年制大学 (統合カリキュラム) | 国立:年間80-100万円 私立:年間150-200万円 4年総額:400-800万円 | 4年間 (看護師+助産師課程) | ✅ 看護学士号取得 ✅ 幅広い教養教育 ✅ 研究能力の育成 ✅ 就職先の選択肢豊富 ✅ 大学院進学への道筋 | ❌ 学費が高額 ❌ 助産師課程への選抜あり ❌ 期間が長い ❌ 競争率が高い | 🎯 高校卒業後すぐ 🎯 学術的な学びを重視 🎯 将来的に大学院進学を考慮 🎯 経済的余裕がある |
| 大学院 (助産学専攻) | 国立:年間80-120万円 私立:年間150-250万円 2年総額:200-500万円 | 2年間 (修士課程) | ✅ 修士号(助産学)取得 ✅ 高度な専門知識習得 ✅ 研究活動への参加 ✅ 教育者・研究者への道 ✅ 少人数教育 | ❌ 学費が高額 ❌ 入学競争が激しい ❌ 研究論文作成必須 ❌ 学部卒業が前提 | 🎯 看護系大学卒業者 🎯 研究志向が強い 🎯 将来的に教育・研究職希望 🎯 高度な専門性を追求 |
| 助産師養成所 (専門学校) | 年間:100-180万円 1年総額:100-180万円 | 1年間 (集中カリキュラム) | ✅ 最短期間での資格取得 ✅ 実践的な教育内容 ✅ 学費が比較的安い ✅ 現場経験豊富な教員 ✅ 即戦力として就職 | ❌ 学習内容が詰め込み式 ❌ 1年間の高強度学習 ❌ 研究活動は限定的 ❌ 学歴は専門学校卒 | 🎯 看護師経験がある 🎯 早期に資格取得したい 🎯 実践重視の学習を希望 🎯 経済的負担を抑えたい |
| 大学専攻科 (助産学専攻科) | 国立:年間60-80万円 私立:年間120-180万円 1年総額:60-180万円 | 1年間 (学士レベル) | ✅ 大学レベルの教育 ✅ 学費が比較的安い ✅ 充実した設備・環境 ✅ 大学の研究活動参加可能 ✅ 学士(助産学)取得 | ❌ 設置校が限定的 ❌ 入学競争が激しい ❌ 1年間の集中学習 ❌ 募集人員が少ない | 🎯 大学レベルの教育希望 🎯 研究にも関心がある 🎯 費用対効果を重視 🎯 設備の充実を求める |
| 短期大学専攻科 (助産学専攻科) | 年間:80-150万円 1年総額:80-150万円 | 1年間 (短大レベル) | ✅ 実践重視の教育 ✅ アットホームな環境 ✅ 個別指導が充実 ✅ 地域密着型教育 ✅ 学費が中程度 | ❌ 設置校が少ない ❌ 研究活動は限定的 ❌ 知名度が低い場合がある ❌ 進学先選択肢が少ない | 🎯 実践的な学習を重視 🎯 少人数教育を希望 🎯 地域で活動したい 🎯 個別サポートを求める |
学習期間別の詳細比較
| 期間 | 対象学校 | 学習の特徴 | 適している人 |
|---|---|---|---|
| 1年間 | 助産師養成所、専攻科 | 集中的で高密度な学習、実習中心 | 看護師経験者、早期資格取得希望者 |
| 2年間 | 大学院 | 研究活動と実践のバランス、論文作成 | 研究志向、高度専門性追求者 |
| 4年間 | 4年制大学統合カリキュラム | 基礎から応用まで段階的、教養教育含む | 高校卒業者、総合的な学習希望者 |
学費負担軽減の方法と選択基準
国公立 vs 私立の選択基準
| 比較項目 | 国公立 | 私立 |
|---|---|---|
| 学費 | 年間60-120万円 | 年間150-250万円 |
| 入学難易度 | 非常に高い | 高い~中程度 |
| 教育の質 | 非常に高い | 学校により差がある |
| 設備 | 充実している | 学校により差がある |
| 就職サポート | 公的病院への就職に有利 | 幅広いネットワーク |
学校選択のための重要チェックポイント
教育環境・設備面
実習設備の充実度
- 分娩室・産褥室の実習設備
- 新生児ケア用の設備・機器
- シミュレーション教育環境
- 図書館・学習スペースの充実
実習先の質と多様性
- 提携病院の規模と症例数
- 正常分娩から異常分娩まで幅広い実習機会
- 地域の助産院での実習機会
- 実習指導者の指導力
就職・キャリア支援
就職実績と就職率
- 過去5年間の就職率(95%以上が目安)
- 就職先の内訳(病院・助産院・行政等)
- 卒業生の活躍状況
- 就職活動サポート体制
国家試験合格率
- 過去5年間の合格率(95%以上が理想)
- 不合格者への再受験サポート
- 試験対策の充実度
学校見学・説明会での確認事項
説明会で必ず質問すべき項目
教育内容について
- 「分娩介助実習では何例程度の介助経験ができますか?」
- 「正常分娩以外の症例も経験できますか?」
- 「実習先での指導体制はどうなっていますか?」
学生サポートについて
- 「学習面でのサポート体制はありますか?」
- 「経済的な支援制度はありますか?」
- 「社会人学生への特別な配慮はありますか?」
卒業後について
- 「卒業生の主な就職先はどこですか?」
- 「就職活動のサポートはありますか?」
- 「卒業後の相談窓口はありますか?」
学校選択の成功事例
事例1:費用重視で国立大学専攻科を選択(Hさん・30歳) 「看護師として5年働いた後、経済的負担を抑えるため国立大学の専攻科を選択しました。倍率は高かったですが、しっかりとした準備で合格。学費は年間80万円で、教育の質も非常に高く大満足です」
事例2:研究志向で大学院を選択(Iさん・28歳) 「将来的に助産師の教育に携わりたいと考え、大学院を選択しました。2年間で修士号を取得し、現在は大学病院で働きながら博士課程進学を準備中です。研究活動の経験が現在の仕事にも活かされています」
事例3:実践重視で助産師養成所を選択(Jさん・35歳) 「2児の子育て中だったため、最短期間で資格取得できる養成所を選択しました。1年間は本当に大変でしたが、実践的な教育で即戦力として就職できました。家族の協力があってこそ実現できました」
まとめ:あなたに最適な学校選択のフローチャート
Step1:現在の状況を確認
- 看護師資格の有無
- 経済的な準備状況
- 家族の理解と協力
- 学習に充てられる期間
Step2:優先順位を決定
- 学費の安さを重視
- 教育の質を重視
- 期間の短さを重視
- 研究活動への参加を重視
Step3:候補校の絞り込み
- 条件に合う学校をリストアップ
- 立地・通学の利便性を確認
- 入学試験の難易度を確認
Step4:詳細情報の収集
- 学校説明会への参加
- 卒業生からの情報収集
- 実際の見学・体験
Step5:最終決定
- 受験校の決定
- 入学試験対策の開始
- 合格後の準備計画策定
この比較表と選択指針を参考に、あなたの状況と目標に最も適した助産師養成課程を見つけてください。慎重な学校選択が、助産師としての充実したキャリアの第一歩となります。
助産師国家試験の難易度・合格率と勉強法
助産師を目指す多くの方が抱く不安の一つが「国家試験に合格できるか」ということです。この章では、試験の実態と効率的な対策方法を詳しく解説し、あなたの不安を解消します。
助産師国家試験の合格率と難易度の真実
令和5年度の合格率は98.4%という高水準
厚生労働省が発表した最新データによると、令和5年度の助産師国家試験合格率は98.4%でした。過去10年間を見ても、合格率は95%以上を維持しており、他の医療系国家試験と比較して非常に高い水準にあります。
過去5年間の合格率推移:
- 令和5年:98.4%(受験者数:2,084名、合格者数:2,051名)
- 令和4年:99.6%(受験者数:2,168名、合格者数:2,159名)
- 令和3年:99.4%(受験者数:2,189名、合格者数:2,176名)
- 令和2年:99.5%(受験者数:2,280名、合格者数:2,268名)
- 令和元年:99.1%(受験者数:2,279名、合格者数:2,258名)
参考:厚生労働省「助産師国家試験の施行」
なぜ合格率が高いのか?受験までのハードルが真の難しさ
高い合格率を見て「助産師国家試験は簡単」と考えるのは誤りです。実際の難しさは、受験資格を得るまでのプロセスにあります。
受験資格取得までの高いハードル
助産師国家試験を受験するまでには、以下の厳しい関門をクリアする必要があります:
看護師資格の取得 まず看護師国家試験に合格し、看護師として登録されている必要があります。この時点で一定の医学・看護学の基礎知識が身についています。
助産師養成課程への入学競争 助産師養成校の入学倍率は2-5倍程度と非常に高く、成績優秀者のみが選抜されます。この段階で学習能力の高い学生が絞り込まれます。
厳格な養成課程の修了 1年間(または2年間)の養成課程では、講義、演習、実習すべてにおいて厳しい評価基準が設けられています。単位を一つでも落とせば国家試験の受験資格を失います。
分娩介助実習での実技習得 正常分娩10例以上の介助を実際に体験し、すべてで合格評価を得る必要があります。この実習で不合格になれば受験資格を得られません。
つまり、国家試験の受験者は既に多くの選抜を経た、高い学習能力と実践能力を持つ人材に限定されているのです。
助産師国家試験の出題内容と傾向
助産師国家試験は75問(必修問題30問、一般・状況設定問題45問)で構成されています。
主な出題範囲
必修問題(30問):助産師としての基本的知識
- 基礎助産学(助産師の責務、倫理、法的規制)
- 助産診断・技術学(妊娠・分娩・産褥の正常経過)
- 地域母子保健(母子保健行政、健康教育)
- 助産管理(助産所管理、医療安全)
一般問題(30問):専門的知識の応用
- 母性看護学・助産学の応用
- 新生児学・小児保健
- 産科学・婦人科学の基礎知識
- 薬理学・病理学の母子への応用
状況設定問題(15問):実践的判断力
- 妊娠期の異常とその対応
- 分娩期の緊急事態への対処
- 産褥期の合併症管理
- 新生児の異常と家族支援
近年の出題傾向の変化
最近の試験では以下のような傾向が見られます:
多職種連携の重視 医師、保健師、ソーシャルワーカーなど他職種との連携に関する出題が増加しています。
地域母子保健の強化 在宅ケア、育児支援、虐待予防など、地域での母子保健活動に関する問題が重視されています。
安全管理の徹底 医療安全、感染対策、リスク管理に関する出題が年々増加しています。
効率的な学習スケジュールの立て方
助産師養成課程は非常にタイトなスケジュールのため、計画的な学習が合格の鍵となります。
養成課程在学中の学習スケジュール
4月-6月(基礎固め期)
- 重点科目:基礎助産学、助産診断学
- 学習時間:平日2-3時間、休日4-5時間
- 学習方法:講義の復習中心、基本概念の理解
この時期は助産学の基礎概念をしっかりと理解することが重要です。看護学で学んだ知識と関連付けながら、助産師特有の視点を身につけましょう。
7月-9月(応用力養成期)
- 重点科目:助産技術学、母性看護学応用
- 学習時間:平日3-4時間、休日5-6時間
- 学習方法:事例検討、技術演習の復習
実習前のこの時期は、理論と実践を結びつける学習が中心となります。様々な事例を通じて、判断力を養いましょう。
10月-12月(実習と並行学習期)
- 重点科目:実習での経験を理論で補完
- 学習時間:実習の合間の時間を最大活用
- 学習方法:実習記録の作成、事例の振り返り
実習期間中は時間が限られますが、実際の経験を理論と照らし合わせることで、深い理解が得られます。
1月-2月(直前対策期)
- 重点科目:過去問演習、弱点補強
- 学習時間:平日4-5時間、休日8時間以上
- 学習方法:過去問題集、模擬試験、グループ学習
科目別学習のポイント
基礎助産学 助産師の法的責務、倫理について確実に押さえましょう。特に「助産師ができること・できないこと」の境界線は重要な出題ポイントです。
助産診断・技術学 正常な妊娠・分娩・産褥の経過を完璧に理解し、異常の早期発見ができるレベルまで習得することが必要です。
地域母子保健 母子保健法、児童福祉法などの法的知識と、実際の保健指導技術の両方をバランス良く学習しましょう。
合格率向上のための実践的テクニック
過去問題の効果的な活用法
過去5年分の問題を最低3回は繰り返し解きましょう。ただし、単に暗記するのではなく、以下の手順で学習することが重要です:
Step1:問題の背景理解 なぜその選択肢が正解なのか、他の選択肢がなぜ間違いなのかを理論的に理解します。
Step2:関連知識の整理 一つの問題から派生する関連知識を整理し、知識の体系化を図ります。
Step3:実践場面での応用 実習での経験と照らし合わせて、実際の場面でどう活用するかを考えます。
効果的な暗記テクニック
助産師試験では覚えるべき数値や基準値も多くあります:
数値記憶のコツ
- 正常値と異常値をセットで覚える
- 語呂合わせや関連付けを活用する
- 視覚的なイメージと組み合わせる
法的知識の整理
- 法律名、条文番号、具体的内容を体系的に整理
- 実際の業務での適用場面と関連付ける
グループ学習の活用
同期の仲間とのグループ学習は非常に効果的です:
互いに教え合う 自分が理解した内容を人に説明することで、知識が確実に定着します。
情報共有 各自が得意な分野の情報を共有することで、効率的に学習範囲をカバーできます。
モチベーション維持 一人では挫折しがちな直前期の学習も、仲間がいることで続けられます。
試験当日の心構えと対策
体調管理の重要性
試験1週間前からは新しい知識の詰め込みよりも、体調管理を優先しましょう:
- 規則正しい睡眠時間の確保(最低7時間)
- バランスの取れた食事
- 適度な運動とリラックス時間
試験当日の戦略
時間配分の計画
- 必修問題:45分(1問1.5分)
- 一般問題:45分(1問1.5分)
- 状況設定問題:30分(1問2分)
解答順序の工夫 得意分野から解き始めて、自信を持って後半に臨みましょう。
見直しの徹底 すべての問題を解き終えたら、必ず見直しの時間を確保してください。
不合格だった場合の対策
万が一不合格だった場合でも、諦める必要はありません。
次年度受験への準備 合格基準に達しなかった分野を特定し、重点的に学習し直します。養成校の教員や同期と相談しながら、効果的な学習計画を立て直しましょう。
精神的サポートの活用 不合格の精神的ショックは大きいものですが、家族や友人、指導教員のサポートを受けながら、前向きに再挑戦することが重要です。
助産師国家試験は確かに専門的な知識を問う試験ですが、養成課程をしっかりと修了していれば合格は十分可能です。計画的な学習と適切な対策により、あなたも必ず合格を勝ち取ることができるでしょう。
助産師になるために必要な資格
助産師になるためには、以下の資格を取得する必要があります。
では、それぞれ見ていきましょう。
看護師資格
まずは、看護師国家試験に合格し「看護師資格」を取得します。
看護師国家試験について
- 試験実施日:毎年2月中旬の日曜日
- 合格率:89.2% (新卒者94.7%)
- 筆記試験
…基礎看護学、成人看護学、小児看護学、母性看護学、精神看護学、人体の構造と機能、疾病の成り立ちと回復の促進、在宅看護論および看護の統一と実践、健康支援と社会保障制度
参照:厚生労働省
例年10月に受験願書が配布され、11~12月が書類の提出期間となるため、計画的な準備が必要です。
助産師資格
つぎに、助産師国家試験の合格者が得られる「助産師資格」を目指します。
助産師国家試験について
- 試験実施日:毎年2月に実施
- 合格率:99.4%(新卒者99.5%)
- 筆記試験の内容
…基礎助産学、助産技術学、助産診断学、地域母子保健、助産管理
参照:厚生労働省
受験願書の配布期間と書類の提出期間は、看護師試験と同様です。
助産師試験に合格しても、看護師試験に不合格の場合、資格を得られないという点に注意しましょう。
【必見】助産師になるまでに費用は80~150万円かかる!
助産師になるまでには、80~150万円かかります。
助産師養成校の学費目安
- 国公立の大学:100万円前後
- 私立の大学:150万円~
- 専門学校:80万円前後
参考:日本の学校
国公立の学校であれば費用を抑えることができますが、その分競争率も高くなります。
また、これはあくまで受講費であるため、このほかに入学金や実習費、教材費が追加で必要です。
総額はこれを上回ることとなるでしょう。
看護師学校の通学にかかる費用
看護師学校の費用相場
- 専門学校:約250~300万
- 私立大学は約500~700万円
- 通信講座(2年/准看護師→看護師を目指す場合のみ):約90万円前後
※参考:ベスト進学ネット
費用は学校・コースによって異なります
このように、看護師資格取得までの時点で、高額な費用がかかることを理解しておかなければなりません。
補足:学費免除を受けることができる
養成校の学費を抑える方法は、主に以下の3つです。
それぞれの特徴を解説します。
(1). 特待生制度
成績優秀な学生が利用できる制度です。
一定以上の成績を収めた学生が対象となります。
具体的な内容や条件は学校によって異なりますが、受講費が全額あるいは半額免除になる場合があります。
(2). 奨学金制度
所定の条件を満たすことで、奨学金を得られる制度も用意されています。
看護系の学校では「卒業後、学校指定の医療機関で3~5年就業することで返済義務が免除される」という仕組みの奨学金が一般的です。
それゆえ、就業先が限定されてしまうという注意点も存在します。
奨学金の「受給要件」や「返済義務」について事前に調べた上で、自分に合うものを選択しましょう。
(3). 社会人向けの給付金制度
一度他業種で働いたのち、医療業界へのキャリアチェンジを考えている方は、「教育訓練支援給付金」を得られる可能性があります。
これは厚生労働省が人材開発を目的として行っている施策のひとつで、教育訓練の受講に必要な費用の一部が支給されるというものです。
「45歳未満の退職後1年以内に学校の授業を受ける人」が対象となります。
詳しい受給要件については、厚生労働省ホームページを参考にしてください。
助産師に向いている人の4つの特徴
助産師に向いている人には、以下の4つの特徴があります。
では見ていきましょう。
体力に自信がある
助産師に向いている人の特徴として、体力に自信があるということが挙げられます。
というのも、出産が長引くことにより、超過勤務になることがあるからです。
助産師さんめっちゃ体力いるしニコニコしなきゃだし本当に働いてる人すごいなって思った。
何時間も人の腰さすったり押したりってだけでも本当大変だと思う。
それゆえ、長時間にわたり母子をサポートできる体力が必要だといえます。
メンタルが強い
メンタルが強い人も、助産師に向いているといえます。
なぜなら、時には流産などの悲しい場面に立ち会うことがあるからです。
そのため「命の誕生に立ち会える」という幸せなイメージだけでは、助産師を続けていくのが難しいでしょう。
したがって、悲しいことが起きても「もっと勉強して次のお産に備えよう」と思えるメンタルの強さは必要です。
思いやりの気持ちがあり、寄り添える
助産師には、思いやりの気持ちも大切です。
妊婦さんは、子どもを産むことに対し少なからず不安を抱えているでしょう。
そのため、妊婦さんに寄り添い「安心感を与える」ことは、助産師の大きな役目だといえます。
人の世話が好き
人の世話が好きな人も、助産師に向いています。
というのも、分娩前後に体を思うように動かせない妊婦さんのお世話をすることは、助産師の重要な仕事だからです。
サポートをする際は、親子に向き合い、会話や表情から要望を読み取らなくてはなりません。
それゆえ助産師の仕事は、人と触れ合うことや、世話をすることが好きな人に適しているといえます。
【要注意】助産師に特有の仕事の苦労
助産師の仕事には、以下のような苦労もあります。
それでは、1つずつ解説していきます。
労働時間が変則的
助産師の仕事は労働時間が不規則になりがちです。
というのも、お産は「いつ始まるか」予測できないからです。
夜勤や休日出勤、緊急呼び出しなどもあり、お産が長引くと勤務時間が延びることもあります。
命を預かる責任が重い
以下の通り、命を預かる責任の重さが、辛いと感じる方も多いです。
助産師になれたこと誇らしいし、この仕事はすごいなって思う
けど、働いてみてこの時期になってくるの新人にもしっかり責任がついてくる、時々これからずっとこんな責任ついてくるのかな〜と思うとしんどくなる、こわい、
出典「Twitter」
また出産は、医療訴訟の多い分野でもあります。
ゆえに、常に責任感を持って、命に向き合わなくてはなりません。
認知度が低い
以下の口コミから分かる通り、助産師の認知度は低く、専門性を認められないこともあります。
昨日?透明なゆりかごの再放送があったらしく、友達がインスタに本当にいい仕事に就いたね!と書いてくれていた。
助産師の仕事って、日本ではまだまだ知られてないから、仕事の良さが伝わって、これからなりたい子が増えることを願いたい。
出典「Twitter」
事実、世間からは「看護師さんと同じではないの?」という風に受け止められる場合があります。
助産師の仕事に対する理解の深まりや、地位向上は、今後の課題だといえます。
そもそも助産師の仕事とは?
助産師とは、助産所・産婦人科で、出産の介助を行う仕事です。
「保健師助産師看護師法」のもと、国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けることで助産師として働くことができるようになります。
なお、日本国内では助産師になれるのは女性のみです。
では、上記の項目について、解説していきます。
助産師の仕事の幅は広がっている
助産師の仕事の幅は、広がりを見せています。
というのも、不妊治療や産後ケアなど、需要が増している分野もあるからです。
実際に助産師ができる仕事の例として、以下が挙げられます。
| 助産師の主な業務内容 | その他、助産師ができる仕事 |
|
|
さらに、今後は高齢出産などの「ハイリスク分娩」に対応できる知識を持つことも必要となるでしょう。
日本には助産師が約4万1千人いる
日本の助産師の総数は、約4万1千人です(出典:『令和2年 看護関係統計資料集』日本看護協会出版会編集)。
その中でも、病院で勤務する助産師は23, 199人と、全体の57.1%を占めています。
他にも、以下のような職場で働く助産師がいます。
- 診療所
- 助産所
- 看護師等学校養成所・研究機関
- 市区町村
産婦科医・助産師が不足している施設では助産師の需要が高く、活躍が望めます。
助産師の平均年収は450~510万円
助産師の平均年収は450万円~510万円程であると言われています。
年代別の平均年収目安は以下の通りです。
| 20代 | 280~350万円 |
| 30代 | 300~400万円 |
| 40代 | 400~580万円 |
| 50代 | 500~600万円 |
| 60代 | 350~580万円 |
なお、国家公務員として働く助産師の平均年収は、約555万円と、さらに高くなっています。(スタディサプリ)
看護師よりも高給であることが多い
看護師の平均年収は、およそ479万円であると言われており、助産師は看護師に比べ年収が高く設定されていることが一般的です。
看護師資格に加えて助産師資格も取得する必要があるため、助産師として働ける人は相対的に少なくなります。
そのため、助産師のニーズは常に高く、給与も高水準となっているのです。
助産師の仕事は数十年後もなくならない!
助産師の仕事は、20~30年後もなくならないと言えるでしょう。
なぜなら、少子化といえど、生まれてくる子どもたちがいるからです。
ただ、不妊治療など、必要な知識や求められる役割は変化していきます。
したがって、時代の流れに沿って勉強を続けていくことが大切です。
【FAQ】助産師を目指す方によくある質問
看護師を目指す際によくある質問をまとめました。
疑問点がある方は、ここで解消しておきましょう。
Q. 助産師試験の合格率はどのくらいですか?
2020年2月に実施された助産師国家試験の合格率は、以下のようになりました。
| 受験者数 | 2,105人 |
| 合格者数 | 2,093人 |
| 合格率 | 99.4% |
どの年も平均して、合格率は90%後半を維持しており、受験年による大きな差異は生じていません。
Q. 助産師の就業先はどのような施設がありますか?
助産師の就業先は、「病院」と「診療所」が9割を占めます。
たいていの場合、総合病院や大学病院、産婦人科・小児科病院などの医療機関で働くこととなるでしょう。
その一方でわずかではありますが、助産院や保健所で働くという助産師もいます。
Q. 社会人から目指すのは何歳くらいまで現実的ですか?
A. 結論から言うと、40代前半までであれば十分現実的です。ただし、年齢よりも重要なのは本人の意欲と体力、そして家族の理解です。
年代別の現実的な考察:
20代後半-30代前半:最適な転職時期 この年代は体力もあり、まだ家庭の責任も比較的軽いため、最も転職に適した時期です。実際に多くの社会人がこの時期に助産師への道を選択しています。
30代後半-40代前半:計画的アプローチが必要 家庭や経済的責任が増える時期ですが、十分可能です。ただし、家族の協力と綿密な計画が不可欠になります。
実際の成功事例:39歳で助産師になったCさん 「銀行員から転職しました。子どもが小学校に上がったタイミングで看護学校に入学し、7年かけて助産師になりました。年齢的な不安もありましたが、人生経験を活かして患者さんとの信頼関係を築けています。同期より給与は下がりましたが、やりがいは計り知れません」
40代後半以降:個別判断が必要 不可能ではありませんが、体力面や学習面でのハードルが高くなります。ただし、豊富な人生経験は助産師としての大きな武器になります。
年齢を重ねた転職のメリット:
- 人生経験に基づく深い共感力
- 妊産婦や家族との信頼関係を築きやすい
- 落ち着いた判断力と包容力
- 多様な価値観への理解
注意すべきポイント:
- 体力的な負担(夜勤、立ち仕事への適応)
- 新しい知識の習得への柔軟性
- 年下の同期や指導者との関係性
- 経済面での長期計画の必要性
Q. 臨床経験がなくても助産師になれますか?
A. 看護師資格があれば臨床経験なしでも助産師になることは可能ですが、実際には臨床経験があった方が有利です。
臨床経験なしの場合の対策:
助産師養成校での選考への影響 多くの養成校では、看護師としての臨床経験(1-2年以上)を推奨または要求しています。経験がない場合は、以下の点でアピールする必要があります:
- 看護学生時代の実習での積極的な取り組み
- 助産師を目指す明確な動機と将来ビジョン
- 自主的な学習や研修への参加経験
- ボランティア活動などでの社会貢献経験
実習での困難と対策 臨床経験がないと、助産師養成課程の実習で以下の困難を感じる場合があります:
患者さんとのコミュニケーション → 事前に接遇研修を受ける、先輩や教員にアドバイスを求める
医療技術への不安 → 基本的な看護技術を事前に復習、練習を重ねる
緊急時の判断力不足 → シミュレーション学習を積極的に活用、事例検討を重ねる
成功事例:新卒で助産師養成校に進学したDさん 「看護師として働かずに直接助産師養成校に進学しました。実習では経験不足を痛感しましたが、基礎からしっかり学ぶ姿勢を評価していただき、指導者の方々に手厚くサポートしてもらえました。現在は新人助産師として日々成長しています」
学習・勉強に関する質問
Q. 文系出身で数学や理科が苦手なのですが、不利になりますか?
A. 文系出身でも全く問題ありません。実際に多くの文系出身者が助産師として活躍しています。
文系出身者が活かせる能力:
コミュニケーション能力 妊産婦や家族との関わりでは、理系的な知識よりも共感力や表現力が重要になります。文系の学習で培った言語能力は大きな武器になります。
文章作成能力 看護記録、助産録、指導計画書など、助産師の業務では多くの文書作成が必要です。文系で鍛えた文章力が活かされます。
人文社会科学的視点 妊娠・出産は医学的な出来事であると同時に、社会的・文化的な意味を持ちます。文系的な広い視野は助産師として非常に価値があります。
理系科目への対策方法:
基礎から段階的に学習 高校レベルの生物・化学から復習し、段階的に医学的知識に進みます。
視覚的学習の活用 図表、模型、動画などを活用して、抽象的な概念を具体的にイメージします。
実践と関連付け 「なぜこの知識が必要なのか」を常に実践と関連付けて理解します。
成功事例:文学部出身のEさん 「大学では文学を専攻していましたが、看護学校では生物・化学が最初は本当に大変でした。でも、『妊産婦さんを理解するために必要な知識』と思うと頑張れました。今では、文学で培った感性が助産師としての強みになっています」
Q. 助産師学校の面接ではどのようなことを聞かれますか?
A. 助産師養成校の面接では、志望動機、適性、将来性を中心に質問されます。事前の準備が合否を大きく左右します。
頻出質問と回答のポイント:
志望動機に関する質問
- 「なぜ助産師を目指すのですか?」
- 「助産師と看護師の違いをどう理解していますか?」
- 「当校を志望する理由は何ですか?」
回答のポイント: 具体的な体験やエピソードを交えて、説得力のある動機を述べる。単に「赤ちゃんが好き」ではなく、母子の健康支援への使命感を示す。
適性に関する質問
- 「助産師に必要な資質は何だと思いますか?」
- 「ストレスの多い場面でどう対処しますか?」
- 「チームワークが重要な場面での経験を教えてください」
回答のポイント: 自分の経験を通じて、助産師に必要な資質を身につけていることを具体的に示す。
学習に関する質問
- 「1年間の学習についていく自信はありますか?」
- 「看護師としての経験を助産師にどう活かしますか?」
- 「苦手な分野があればどう克服しますか?」
将来に関する質問
- 「助産師になったらどんな分野で働きたいですか?」
- 「5年後、10年後のキャリアプランは?」
- 「地域の母子保健にどう貢献したいですか?」
面接対策のポイント:
事前準備の徹底
- 学校の教育理念や特色を詳しく調べる
- 自分の経験や考えを整理し、簡潔に述べられるよう練習
- 助産師の現状や課題について情報収集
模擬面接の実施 家族や友人に協力してもらい、実際の面接形式で練習します。
身だしなみと態度 清潔感のある服装、明るい表情、はきはきとした話し方を心がけます。
家庭との両立に関する質問
Q. 子育てや現在の仕事と、学校の勉強は両立できますか?
A. 綿密な計画と家族の協力があれば両立可能ですが、相当な覚悟と工夫が必要です。
両立成功の条件:
家族の理解と協力 最も重要なのは家族の理解です。特に以下の点で協力を得る必要があります:
- 家事・育児の分担
- 学習時間の確保への理解
- 実習期間中の子どもの世話
- 経済面での協力
時間管理の徹底 限られた時間を最大限活用するための工夫:
早朝学習の活用 子どもが起きる前の5:00-6:00の1時間を学習時間に確保
スキマ時間の有効活用 通勤時間、昼休み、子どもの習い事待ち時間などを暗記時間に活用
週末の集中学習 土日のうち半日は集中学習時間として家族に協力してもらう
実習期間の準備 最も困難なのが実習期間です:
事前準備
- 実習スケジュールの早期把握
- 一時保育や学童保育の手配
- 親族や友人への協力依頼
- 緊急時のサポート体制構築
両立成功事例:2児の母Fさん 「小学2年と年長の子どもを育てながら助産師養成校に通いました。夫の協力はもちろん、両親や義両親にも頼み、一時保育も活用しました。実習期間は本当に大変でしたが、『子どもたちに頑張る姿を見せたい』という思いで乗り切りました」
仕事との両立パターン
看護師として働きながら
- 夜勤を減らし、日勤中心の勤務に変更
- パート勤務に変更して学習時間を確保
- 職場の理解を得て、実習期間中は休職
他職種で働きながら
- 時間の融通が利く職場への転職
- 在宅ワークやフリーランスへの転換
- 学習最優先で収入減少を受け入れる
男性と助産師に関する質問
Q. 男性でも助産師になれますか?
A. 現在の日本では、男性は助産師になることはできません。これは法的な制限によるものです。
法的根拠と背景
助産師法第3条により、助産師になれるのは「女子」に限定されています。この規定は以下の理由に基づいています:
文化的・社会的背景
- 出産という女性の最もプライベートな体験への配慮
- 日本の文化的価値観との整合性
- 妊産婦のプライバシー保護
国際的な状況 欧米諸国では男性助産師(Male Midwife)が認められている国もありますが、日本では現在のところ法改正の予定はありません。
男性看護師の選択肢
男性で母子医療に関わりたい場合は、以下の選択肢があります:
産科・小児科看護師 男性看護師として産科病棟やNICU、小児科で働くことは可能です。
保健師 男性でも保健師資格を取得でき、母子保健事業に関わることができます。
医師 産婦人科医や小児科医として母子医療に従事することができます。
成功事例:産科病棟で働く男性看護師Gさん 「助産師になりたかったのですが、法的に不可能なため産科病棟の看護師として働いています。直接分娩介助はできませんが、妊産婦さんやご家族のケア、新生児のケアに携われることにやりがいを感じています」
経済・費用に関する質問
Q. 助産師になるまでにかかる費用はどのくらいですか?
A. 総額で400万円-800万円程度が相場ですが、ルートや学校選択により大きく異なります。
ルート別費用詳細:
高校生から(4-5年間)
- 看護大学4年:400-600万円
- 助産師養成課程1年:100-200万円
- 総額:500-800万円
看護師から(1年間)
- 助産師養成課程1年:100-200万円
- 生活費(収入減少分):200-300万円
- 総額:300-500万円
社会人から(4-5年間)
- 看護師養成課程:200-400万円
- 助産師養成課程:100-200万円
- 生活費:200-400万円
- 総額:500-1000万円
費用軽減の方法:
奨学金・給付金の活用
- 日本学生支援機構奨学金
- 自治体独自の奨学金制度
- 病院の奨学金制度(卒業後の勤務が条件)
- 専門実践教育訓練給付金(最大224万円)
働きながら学ぶ
- 看護助手として働きながら看護学校
- 看護師として働きながら助産師養成校
Q. 助産師の年収や待遇はどの程度ですか?
A. 年収500万円-700万円程度が相場で、看護師より高い傾向にあります。
勤務先別年収目安:
- 総合病院:550-650万円
- 大学病院:600-700万円
- 助産院:400-600万円
- クリニック:450-550万円
助産師の待遇面でのメリット:
- 看護師より基本給が高い設定
- 専門性手当の支給
- 管理職への昇進機会
- 開業権(助産院経営)
これらの FAQ により、助産師を目指す過程での様々な不安や疑問を解消し、より具体的で現実的な計画を立てることができるでしょう。あなたの状況に応じて、最適な道筋を見つけてください。
さいごに
この記事では、助産師を目指すための具体的な手順や必要期間について解説しました。
社会人として働きながらであっても、仕事と勉強を両立しながら、助産師を目指すことは可能です。
勉強方法を工夫したり、勤務を調整しながら、無理なく学んでいきましょう。
資格取得を達成できた場合や、まずは医療業界で働いてみたいという方であれば、以下の転職サイトの利用をおすすめします。
| 転職サイト | 助産師求人 | 利用者満足度 |
| 看護roo! | 550件 | ★★★★☆4.2 看護系転職サイト満足度No1 |
| レバウェル看護(旧 看護のお仕事) | 860件 | ★★★★☆4.0 助産師求人が最多! |
| ナースではたらこ | 220件 | ★★★★☆3.9 逆指名求人が魅力 |
転職サイトについてより詳しく知りたい方は
- 関連記事『助産師の転職サイト目的別おすすめ』
- 関連記事『パート助産師の求人探しにおすすめの転職サイト』
この記事があなたのキャリアに役立つことを願っています。
![転職 – LiPro[ライプロ]| あなたの「暮らし」の提案をする情報メディア](https://www.iid.co.jp/contents-career/wp-content/uploads/2024/10/LiPro_logo_career.jpg)