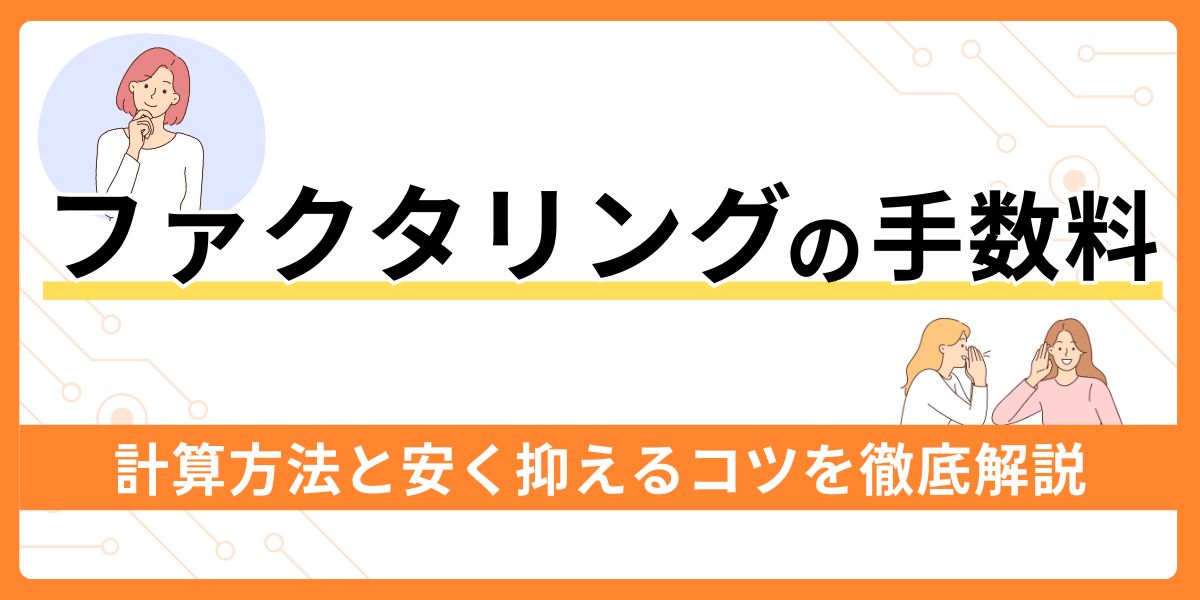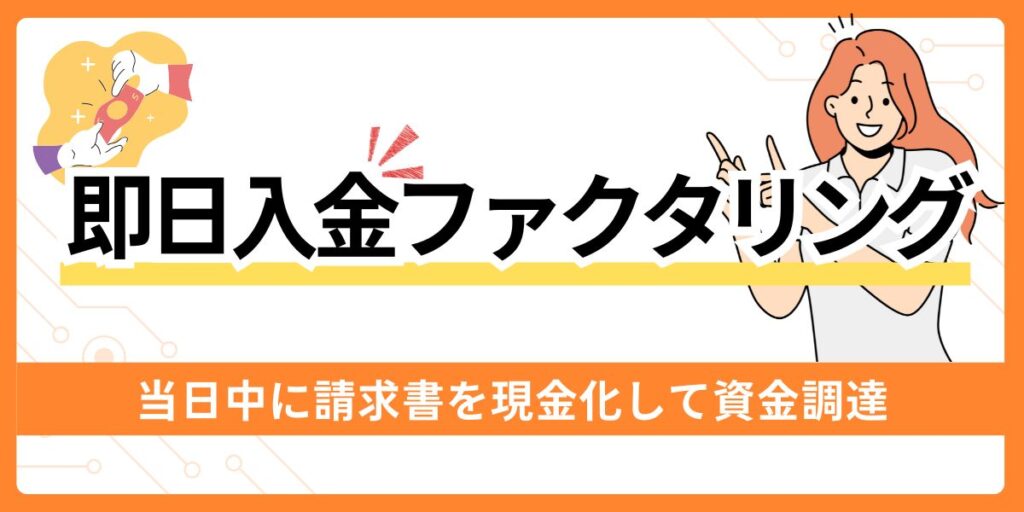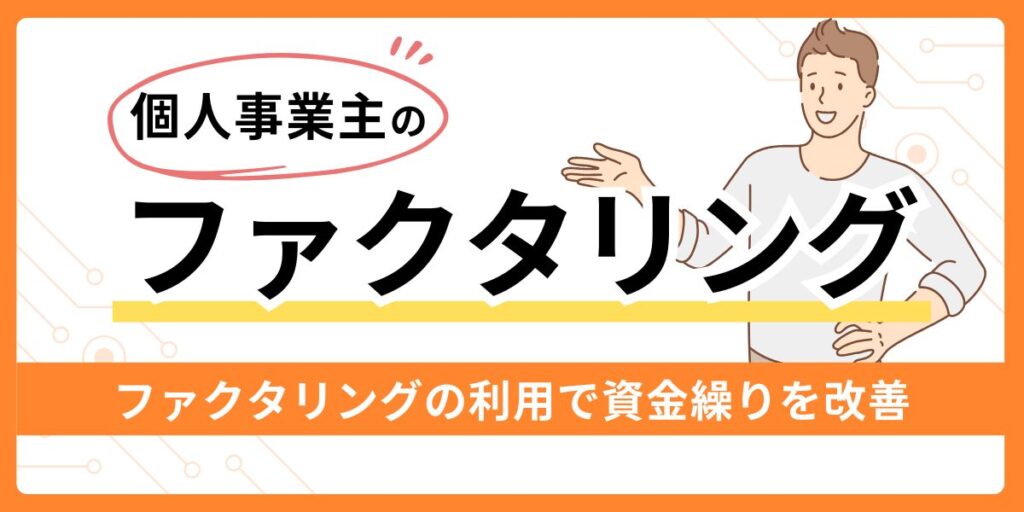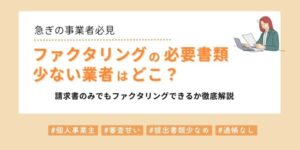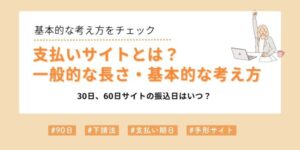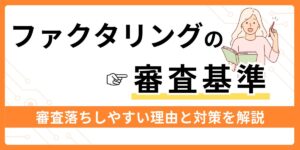ファクタリングは資金繰りに困った企業が売掛金を早期に現金化できる資金調達方法です。
しかし、即日対応を求めると手数料が高くなるのではないかと不安を感じる経営者や経理担当者も多いのではないでしょうか。
ファクタリングの手数料相場や計算方法を知っておくと、適正価格で安心して利用できます。
本記事では即日ファクタリングの手数料の仕組みから相場・計算方法まで詳しく解説します。
当サイトで紹介している日本中小企業金融サポート機構の情報は、信頼性と正確性を重視し、公式サイトだけでなく公的機関や関連団体の情報を参考に作成しております。
具体的には、金融庁や消費者庁などが提供する公開データや指針を基に構成しています。
詳細な編集方針や調査プロセスについては、コンテンツ制作・編集ポリシーをご確認ください。
ファクタリング手数料の基本知識
ファクタリング手数料の基本知識として、以下の2つを解説します。
ファクタリングは売掛金(請求書)を割り引いた金額で買い取るサービス。
例えば100万円の売掛金を90万円で買い取る場合、手数料率は10%です。
即日ファクタリングで資金調達する場合、企業によっては手数料が高くなるケースもあります。
ファクタリングの手数料はファクタリング業者の利益
ファクタリングの手数料は売掛債権を買い取るファクタリング会社の利益源泉です。
通常の融資と異なり貸し倒れリスクをファクタリング会社が負うため、リスク分が手数料に反映されます。
例えば1,000万円の売掛金を売却する場合、手数料として50万円〜150万円程度が差し引かれるのが一般的。
ファクタリング会社は以下のコストとリスクを踏まえて手数料を設定しています。
- 売掛先企業の信用調査コスト
- 債権管理や回収にかかる人件費
- 支払い遅延や未払いリスクへの備え
- 資金調達コスト
手数料はサービス提供の対価であり、速さや確実性を求めるほど高くなる傾向にあります。
2者間ファクタリングと3者間ファクタリングで異なる手数料構造
ファクタリングには2者間と3者間の二つの方式があり、手数料率に大きな違いがあります。
2者間ファクタリングは、資金調達企業とファクタリング会社の間だけで完結するため、手数料率は8%〜18%と高めです。
一方、3者間ファクタリングは売掛先企業も交えた取引で、手数料率は2%〜9%と比較的低く抑えられます。
手数料率の違いは主に以下の要因によるものです。
| ファクタリングの契約方式 | 理由 |
|---|---|
| 2者間ファクタリング | 売掛先企業に知られず取引できる ファクタリング会社の回収リスクが高い |
| 3者間ファクタリング | 売掛先企業の支払い確約があり回収リスクが低い 手続きに時間がかかり即日対応が難しい場合がある |
例えば100万円の売掛金の場合、2者間ファクタリングでは70万〜85万円の資金調達となる一方、3者間ファクタリングでは85万〜95万円と手取り額に大きな差が生じます。
即日での資金調達と手数料のバランスを考慮して、ニーズに合った契約方式を選びましょう。
即日ファクタリングの手数料相場と適正ライン
即日ファクタリングの手数料相場は2者間と3者間で大きく異なり、適正ラインを知ることが重要です。
手数料相場を知っておくことで、不当に高い手数料を請求する悪質業者を避けることができます。
ファクタリング手数料相場の目安【2者間・3者間別】
ファクタリングの手数料相場は、取引形態によって大きく異なります。
- 2者間ファクタリング:8%〜18%
- 3者間ファクタリング:2%〜9%
実際の手数料率は以下の要因によって変動します。
- 売掛先企業の規模や信用度
- 取引実績や過去の支払い履歴
- 売掛金額の大きさ(大口ほど手数料率は下がる傾向)
- 支払期日までの残存期間
- 資金調達の緊急性(即日か数日待てるか)
手数料率が相場を大きく外れる場合は、何らかの問題がある可能性を疑いましょう。
2者間ファクタリングは業者がリスクを負う分手数料が高め
2者間ファクタリングの手数料が3者間より高い理由は、主にリスク負担の違いにあります。
2者間ファクタリングでは売掛先企業に通知せず取引するため、支払い拒否や遅延のリスクがファクタリング会社に集中します。
さらに以下のようなリスクや特性も手数料に影響しています。
- 売掛先企業の承諾がないため法的保護が弱い
- 回収業務をファクタリング会社が担う必要がある
- 即日対応の需要が高く迅速な審査が必要
- 資金繰りに緊急性のある企業が利用するため高めの料率でも受け入れられる
例えば、上場企業への売掛金でも2者間ファクタリングでは15%前後の手数料がかかる一方、3者間なら同じ条件で5%程度に抑えられます。
手数料の差は主にリスクプレミアムであり、資金調達の緊急度と相談しながらファクタリングの契約方式を選択しましょう。
相場より手数料が高い・安い場合は悪徳業者の可能性あり
ファクタリングの手数料が相場よりも著しく高い場合は、悪徳業者の可能性があります。
一方、相場よりも極端に安い場合は、隠れたコストや追加費用が発生するリスクも。
- 30%を超える手数料率は要注意(2者間でも)
- 「審査なし」「ブラックOK」を強調する業者は警戒
- 契約書に記載のない追加費用を請求される可能性
- 手数料の説明が不明瞭な場合は避ける
例えば手数料5%と宣伝していても、実際には事務手数料15%が別途かかるケースもあります。
手数料の透明性と総コストを必ず確認し、契約前に必ず詳細な説明を受けましょう。
ファクタリングの手数料をシミュレーション
ファクタリング手数料がどのように計算されるのか具体的なシミュレーションで理解しましょう。
実際の数字で考えることで、手数料の影響を具体的にイメージできるようになります。
シミュレーション1:請求書の金額が100万円の場合
100万円の請求書をファクタリングする場合の手取り額をシミュレーションします。
- 2者間ファクタリングの場合
-
- 手数料8%:92万円の手取り
- 手数料10%:90万円の手取り
- 手数料18%:82万円の手取り
- 手数料20%:80万円の手取り
- 3者間ファクタリングの場合
-
- 手数料2%:98万円の手取り
- 手数料5%:95万円の手取り
- 手数料9%:91万円の手取り
- 手数料10%:90万円の手取り
同じ100万円の請求書でも、ファクタリングの契約方式や手数料率によって手取り額に差が生じます。
即日で資金が必要な場合でも複数社から見積もりを取りましょう。
シミュレーション2:請求書の金額が500万円の場合
請求書額が大きい500万円のケースでは、少しの手数料率の違いが大きな金額差になります。
- 2者間ファクタリングの場合
-
- 手数料8%:460万円の手取り(40万円の手数料)
- 手数料10%:450万円の手取り(50万円の手数料)
- 手数料18%:410万円の手取り(90万円の手数料)
- 手数料20%:400万円の手取り(100万円の手数料)
- 3者間ファクタリングの場合
-
- 手数料2%:490万円の手取り(10万円の手数料)
- 手数料5%:475万円の手取り(25万円の手数料)
- 手数料9%:455万円の手取り(45万円の手数料)
- 手数料10%:450万円の手取り(50万円の手数料)
額面が大きくなると手数料率の交渉余地も広がり、500万円以上なら標準より1〜3%程度低い料率で交渉できるケースもあります。
シミュレーション3:複数社に見積もりをとった場合の比較例
同じ売掛債権でも複数のファクタリング会社で見積もりを取ると、大きな差が生じることがあります。
実際の500万円の請求書に対する3社の見積もり例を見てみましょう。
- A社(2者間):手数料8%の場合
-
手取り額400万円
- B社(2者間):手数料18%の場合
-
手取り額410万円
- C社(3者間):手数料9%の場合
-
手取り額455万円
急ぎでなければC社を選ぶのが経済的ですが、即日入金が必須ならA社を選ぶことになります。
資金需要の緊急度と手数料のバランスを考慮して選ぶことが重要です。
ファクタリングの手数料に潜むリスクと対策
ファクタリングの手数料には様々なリスクが潜んでいます。
- 手数料が相場とかけ離れているリスク
- 「審査なし」を謳う違法業者の手口
- あとから追加手数料を請求されるパターン
- リスクを回避するチェックポイント
リスクを理解し適切な対策を講じることで、安全にファクタリングを利用できます。
手数料が相場とかけ離れているリスク
ファクタリング手数料が相場と著しく異なる場合は注意が必要です。
特に手数料が極端に低い場合や高すぎる場合には、以下のようなリスクが考えられます。
- 手数料が極端に高い場合のリスク
-
- 出資法違反の可能性
- 過剰な手数料による資金繰りの悪化
- 返金を要求しても応じてもらえない
- 詐欺的なビジネスモデルの可能性
- 手数料が極端に低い場合のリスク
-
- 審査通過後に条件変更される可能性
- 一部しか買い取らないなどの条件がある
- 個人情報収集が目的の業者の可能性
- キャンセル時に高額な違約金を請求される
例えば、2者間で手数料10%と宣伝している業者は、契約直前になって「この条件は別の商品」と言い出し、実際は25%を要求するケースが考えられます。
相場を大きく外れた条件を提示する業者には必ず理由を確認し、契約前に全ての条件を書面で明確にしておきましょう。
「審査なし」と宣伝する違法業者の手口
「審査なし」「ブラックOK」などの文句で宣伝する業者の中には悪質な手口を用いるケースがあります。
- 実質的に貸金業なのにファクタリングと偽装
- 売掛先に取り立てを行う
- 契約書に記載のない高額な手数料を請求
- 実体のない会社を装い前金だけ取って逃げる
ファクタリングは基本的に必ず審査が行われます。
審査落ちが不安なら、審査が甘いファクタリング業者を利用してください。
- 前払い金を要求する業者は避ける
- 実店舗の有無を確認する
- 金融庁の貸金業者登録を確認する
- 口コミや評判を複数のサイトで調査する
- 契約書の内容を慎重に確認する
あとから追加手数料を請求されるパターン
ファクタリングでよくあるトラブルとして、契約後に追加手数料を請求されるケースがあります。
主な手口としては以下のようなパターンがあります。
- 「事務手数料」「調査費用」など名目を変えて請求
- 振込手数料が予想以上に高額
- 売掛金回収のため「特別対応費」を請求
- 支払期日を過ぎると「延長手数料」が発生
- キャンセル料が異常に高額
例えば、契約時には手数料20%としながら、実際の入金時には「事務手数料5%」「システム利用料3万円」などが差し引かれるケースが考えられます。
契約書に「その他必要な費用」といった曖昧な表現がある場合はファクタリング契約前に内容を明確にしてください。
リスクを回避するチェックポイント
ファクタリングを安全に利用するために、契約前に以下のチェックポイントを確認しましょう。
- 手数料率や金額が明確に記載されているか
- 追加費用の項目と金額が全て明記されているか
- キャンセル条件や違約金の金額は妥当か
- 契約解除の条件が明確か
- 売掛金が回収できなかった場合の対応は明記されているか
例えば、法人登記を確認するには国税庁の「法人番号公表サイト」で検索できます。
設立直後の会社や過去に名称変更を繰り返している会社は注意が必要です。
慎重に業者を選び、不明点は必ず質問して明確にしてから契約しましょう。
専門家インタビュー|ファクタリングの手数料を抑えるコツ
ファクタリングの手数料を抑えるコツを、日本中小企業金融サポート機構様にインタビューしました。
- Q1:見積もり金額が妥当かどうかを判断する基準
- Q2:安すぎる手数料をアピールするファクタリング業者について
- Q3:資金繰りが悪化している場合の手数料負担と対策
- Q4:ファクタリング利用の長期的なコストと企業成長への影響
- Q5:外部への通知・信用問題と手数料の関係
専門家の見解を参考に、手数料の相場や手数料を低く抑えるコツについて把握しましょう。
ファクタリング業者選びで迷ったら、日本中小企業金融サポート機構の口コミもチェックしてみてください。
Q1:見積もり金額が妥当かどうかを判断する基準
提示された手数料率が高いのか安いのか、比較のしかたがわからないと考えるファクタリング利用者は多いです。
日本中小企業金融サポート機構様に質問したところ、まず複数社から見積もりを取り、手数料の相場をつかむことが重要だと伺いました。
ファクタリングの手数料が変動する要因は、おもに以下の2つ。
- 2者間と3者間といったファクタリング契約形態の違い
- 売掛先の信用力
売掛先が安定して支払いを行うと見込めれば見込めるほど、リスクが低いと判断され、手数料も下げやすい傾向にあるとのことでした。
Q2:安すぎる手数料をアピールするファクタリング業者について
「手数料最安値」を強調するファクタリング会社を見かけることもありますが、本当に広告どおりの低い手数料が適用されるかどうかは審査次第というお話もありました。
一部のファクタリング業者には、あとから追加費用を請求したり、契約形態が実質的に融資に近いものだったりと悪質な手口があるとのこと。
トラブルを防ぐため、以下5つのポイントを意識すると良いそうです。
- 債権譲渡に関する内容が明記された契約書がある
-
- ファクタリングは融資ではなく売掛金の譲渡契約
- 信頼できる正規のファクタリング会社なら売買契約書や債権譲渡契約を締結する
- 金銭消費貸借契約書を提示された場合は、貸付契約とみなされ悪徳業者の可能性が高い
- 契約書に不審な点がない
-
- 契約書の内容が簡潔でわかりやすいか
- 質問に対して明確な回答を出してくれるか
- 手数料が相場と同等である
-
- 2者間ファクタリング:8%〜18%
- 3者間ファクタリング:2%〜9%
- 相場より高すぎる/低すぎる場合は悪徳業者の可能性
- ファクタリング業界歴が長く取引実績が豊富にある
-
業歴が長く取引実績が豊富なファクタリング業者は、利用者から高い信頼を得ている証拠
- 運営元の情報が公開されている
-
- 会社名・代表者名・住所・連絡先・設立年数・実績などが公開されているか
- ホームページやパンフレットに記載されているかチェック
Q3:資金繰りが悪化している場合の手数料負担と対策
銀行融資が難しいほど資金繰りが逼迫している場合でも、ファクタリングを利用して手数料を抑える工夫はできるそうです。
たとえば、売掛先が安定した企業であれば回収リスクが低いと見なされ、手数料も下げられる可能性が高まるとのことでした。
3者間ファクタリングで売掛先の承諾を得ておけば、ファクタリング会社のリスクをさらに軽減できるため、2者間よりも低めの手数料が提示されるケースが多いようです。
債権譲渡登記も有効な方法ですが、登記にかかる費用や情報が公開されるリスクについても慎重に検討する必要があるというアドバイスもありました。
Q4:ファクタリング利用の長期的なコストと企業成長への影響
ファクタリングは、一時的な資金調達の手段にとどまらず、中長期的な経営戦略の一環として活用する方法もあるといいます。
たとえば、事前に資金を確保しておくことで繁忙期前の仕入れや人員確保をスムーズに行い、売上拡大のチャンスを逃さずに済むとのことでした。
継続的な取引を重ねることで、ファクタリング会社との信頼関係が深まり、手数料を引き下げてもらいやすくなるメリットもあるそうです。
借入とは異なり、ファクタリングは信用情報に大きな影響を及ぼしにくい手段ともいわれています。
金融機関からの融資と併用を検討している場合にも、有効な資金調達方法として位置づけられるようです。
Q5:外部への通知・信用問題と手数料の関係
最後に、取引先へ通知しない2者間ファクタリングでは手数料が高くなりがちだという点についても、具体的な数値でご説明いただきました。
2者間ファクタリングの相場が8〜18%、3者間ファクタリングの相場が2〜9%と、かなりの差があるそうです。
ただし、3者間ファクタリングには売掛先に相談できる関係性や1週間程度の余裕が必要とされる場合があり、2者間よりも手続きが煩雑になることも。
コストを重視するなら3者間ファクタリング、スピードや秘密保持を優先するなら2者間ファクタリングで、状況に応じて選択するのが望ましいとのことでした。
手数料の相場を把握し即日ファクタリングで資金調達しよう
ファクタリングの手数料は、売掛先の信用度や契約の形態によって大きく変動します。
複数社からの相見積もりで手数料の相場を把握することが重要です。
ただ安い手数料を謳う業者に飛びつくのではなく、契約内容や会社情報をしっかり確認し、悪質業者を回避しましょう。
長期的に資金繰りを安定させたい場合には、3者間ファクタリングをはじめとするリスク軽減策や、継続利用による信頼構築なども視野に入れてください。
うまく活用すれば、ファクタリングは経営戦略の一部としても活躍してくれます。
目的や状況に応じた正しい選択と準備が、ファクタリングを成功に導く鍵です。
![副業 – LiPro[ライプロ]| あなたの「暮らし」の提案をする情報メディア](https://www.iid.co.jp/contents-sidejob/wp-content/uploads/2025/03/lipro-logo-factoring.png)